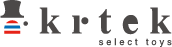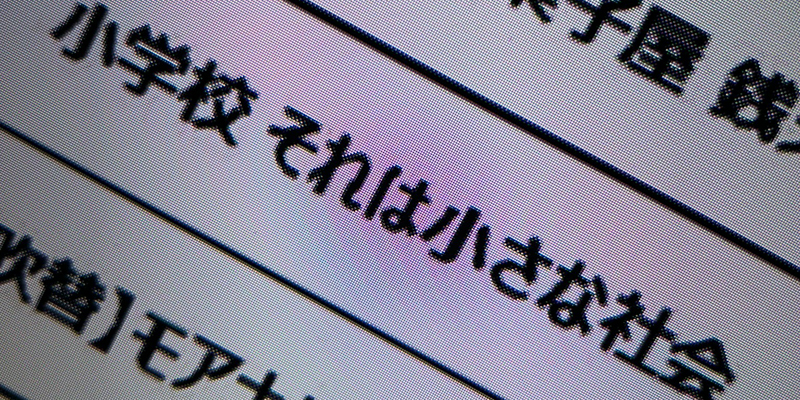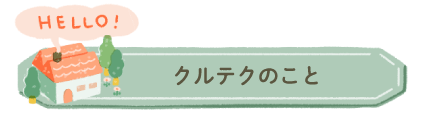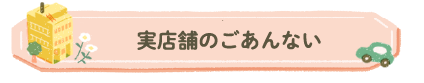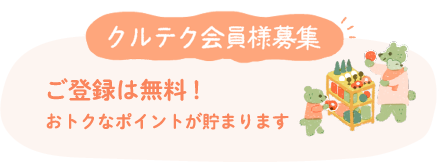この映画の予告編を見たときは、うわー日本の小学校、こういうところがイヤなんだよね、と感じて、批判的に観るつもりでいました。観終わったあとは、うまく批判ができない内容だなあと思いました。
なぜ批判ありきになっていたかをまず考えました。それは、おもちゃ屋という仕事を始めて、幼児期にしっかり遊ぶということが大事だと考えているのに、小学校生活で困らないための準備にその機会が奪われていることに対するものだったのではないかと、思いあたりました。
映画の中で、子どもたちが困っている場面いくつかがありました。そのことで叱られたり、泣いたりしています。我が子にはそんな思いはさせたくない。お行儀や習い事をしっかりさせて、苦労しない小学校生活を送らせてあげたい思いは、親として理解できるものです。その原因をつくったのが小学校のあり方なのではと、協調性や従順を強要するように見える小学校に、矛先を向けていたように思います。
小学校は、どこまで準備して入学してくることを期待しているのだろう。それはよくわからなかったです。映画では、小学校の6年間でちゃんと育てようとイチから丁寧に関わっている様子が描かれていた。ただ、求めている到達度が心に先行して形なのかなと感じます。形に心はちゃんとついてくるのか。
生活面を中心に描いた映画で、学習面はあまり映されていません。学習面では、自分の小学生時代のことは覚えていませんが、自分の子どもの小学校生活を眺めて、つまらないことをやっているなあと感じたことは何度かあります。授業がおもしろくないと、学ぶことに意欲を持てない。授業が成り立つための子どもたちの準備はできているのか。授業を準備する先生の労働環境は整っているのか。できていないとしたら、問題はどこにあるのか。
連帯責任や横並びの程度は、もう少し価値観は変わったほうが良い気がします。できなかったことができるようになったエピソード、それだけ見ていると、成長物語なのですが、他に方法はないのだろうか。「周りに迷惑がかかるから頑張る」という動機づけは、特徴的です。あわせて、「恥をかきたくない」「叱られたくない」も強い感情として育つだろうと思いました。その感情で構成される社会を良しとするのか、どうか。
私自身は、小学校が楽しかったし、大好きな先生がいました。先生になりたくて取った教員免許もあります。丁寧な映画だと思いました。これを機に、広いトピックで考えのシェアが広がると良いです。